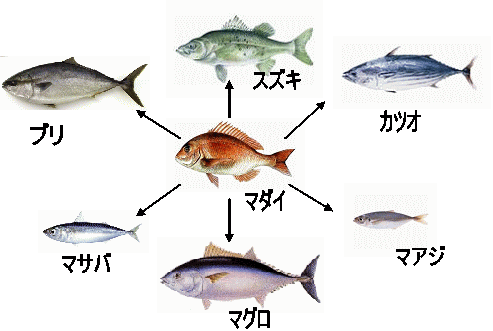- DループDNAの多型解析
- 水産物のミトコンドリアDNAは、核外の小器官に数百コピー分布する核外遺伝子であり、受精卵を通じて仔魚に伝達されます。
その中のDループは、種間だけでなく個体間でも十数塩基の変異が見られます。
他方、真鯛などの人工種苗生産では親魚1尾から数百万尾の稚魚が得られ、系群全体が同じミトコンドリアで標識されています。
このうち、他系群とのDループの変異は前半600塩基内にありました。
弊社は、水産物の肉片やウロコ数枚からDNAを抽出し、両鎖シークエンスで多数の個体識別ができる精度の高い方法を開発し、
水産魚介類のトレーサビリティーと種苗のDNA標識に利用することを提案いたします。
- 水産物の生産履歴管理(トレーサビリティー)
- 日本の食文化は産地や旬の素材を大切にしてきましたが、スーパーやコンビニの普及で、消費者は影形のない切り身や惣菜を食べさせられています。一枚の商品表示で、原産地や輸入食材の偽装は見抜けません。
そこでご提案するのが、DNA表示による生鮮食品の生産履歴管理(トレーサビリティー)です。DNAであれば、そのルーツ(履歴)は消せません。
生鮮食品のうち、水産魚介類はミトコンドリアDループの母系特異的塩基配列を利用します。対照となる魚介類との比較で、
系群から産地識別まで割り出します。
- 養殖種苗のミトコンドリア標識
- 真鯛やまぐろなどのスズキの仲間(下図)は、一回に百万個以上の卵を産みますが、ほとんどは死滅するか、地魚の餌となります。
これを自活できる稚魚まで生け簀内で育てたのが、人工種苗です。誕生日別に採卵すれば稚魚は同じDループで標識され、
子々孫々まで伝達されます。
Dループ配列は、養殖魚のブランド化や知財化に利用できます。
また、海洋放流すれば系群別の生態調査や再生産分を含めた加入量変動調査ができ、栽培漁業の基盤をつくります。
特に、絶滅危惧種では他系群との遺伝的交雑によって回復を早め、漁場を復元させます。
-
回遊性水産物のほとんどを占める真鯛・まぐろの仲間たち (スズキ目)
Dループ塩基配列のデータベース化で系群の配列がわかり、産地・魚種識別ができます
- BACライブラリーと主要組織適合遺伝子(MHC)
- ウィルス抵抗性や量的形質遺伝子(QTL)の特定にはBACライブラリーや主要組織適合遺伝子(MHC)が必要です。
弊社のBACライブラリーや解析技術も併せてご利用ください。
- [ご依頼方法]
注文書に必要事項をご記載の上、電子メールに添付しご送付ください。
試料を弊社にお送りいただく際にも、注文書のコピーを同封頂きますよう、お願いいたします。
※ ミトコンドリア塩基配列未知の魚介類、あるいは分析数が多い場合はご相談ください (E-mail:ginfo@geno-gtac.co.jp)
※ 検査依頼試料は、肉片またはウロコであれば1g程度、調理物・乾物であれば10g程度を冷凍でお送りください。